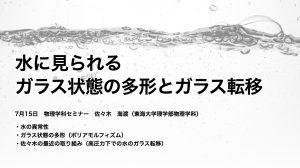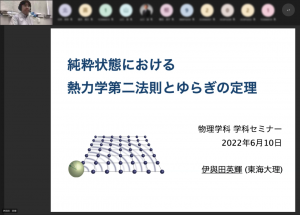物理学科出身で現在は理学研究科の修士課程に在学している塚原さんと小田切さん(新屋敷研究室)が筆頭著者の論文が学術雑誌に掲載されました。
塚原さんが筆頭著者の論文”Dielectric relaxations of ice and uncrystallized water in partially crystallized bovine serum albumin-water mixtures”はRoyal Society of Chemistryが発行する学術雑誌”Physical Chemistry Chemical Physics”に掲載されました。この論文では広帯域誘電分光法を用い、低温下で凍結するタンパク質水溶液中の氷や不凍水の誘電緩和を観測し、その関係や特徴を明らかにしました。塚原さんから「コロナ禍により不便も色々とありましたが、大学院での研究活動の集大成として学術論文を掲載することが出来ました。新屋敷先生にはもちろんのこと、ご指導ご鞭撻を頂いたResearch Group of Molecular complex System(RGMS)の先生方や学生の皆様にも心から感謝しています。」とコメントを頂きました。
Tatsuya Tsukahara, Kaito Sasaki, Rio Kita, and Naoki Shinyashiki
“Dielectric relaxations of ice and uncrystallized water in partially crystallized bovine serum albumin–water mixtures”
Physical Chemistry Chemical Physics, in press
DOI: 10.1039/D1CP05679D
小田切さんが筆頭著者の論文”Interfacial polarization of in vivo rat sciatic nerve with crush injury studied via broadband dielectric spectroscopy”はPLOSが発行する学術雑誌”PLOS ONE”に掲載されました。損傷した神経の再生候補である電気刺激の適切な条件を見つけるために、広帯域誘電分光法を用いた神経インピーダンスの研究が、新屋敷教授の研究室と京都大学の共同で行われ、損傷の有無による界面分極に起因する誘電緩和強度の違いを明らかにしました。その成果をまとめたのが上記の論文です。小田切さんから「他大学の他分野の方々と研究をできたことは、自分の知識や経験を広げる貴重な機会となりました。また、論文が出版できたのは、新屋敷先生、京都大学の先生方や学生、研究室の先輩方のお陰です。感謝しています。」とコメントを頂きました。
Risa Otagiri, Hideki Kawai, Masanobu Takatsuka, Naoki Shinyashiki, Akira Ito, Ryosuke Ikeguchi, Tomoki Aoyama
“Interfacial polarization of in vivo rat sciatic nerve with crush injury studied via broadband dielectric spectroscopy”
PLOS ONE 2021;16(6): e0252589.
DOI: 10.1371/journal.pone.0252589